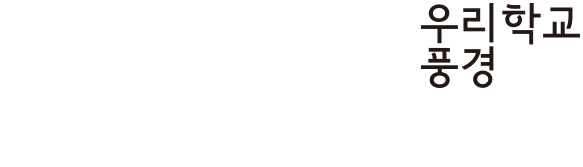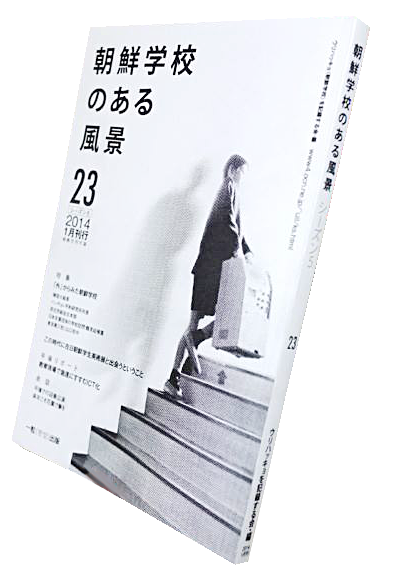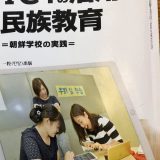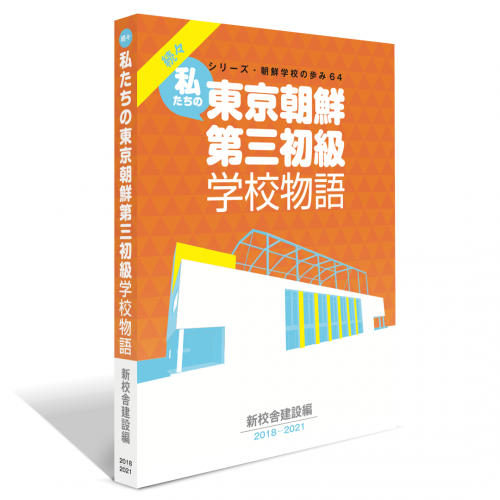朝鮮の春が浮き彫りにした 日本社会の民族差別
スポンサードリンク
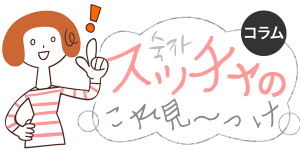
昨年七月、ベルリンで文在寅大統領が「二〇一八年二月、朝鮮半島の軍事境界線から一〇〇キロの距離にある大韓民国平昌で冬季オリンピックが開催されます。…世界の首脳たちがともに拍手を送り、ともに朝鮮半島の平和の新たなスタートを切ることを期待します。北韓の平昌冬季オリンピック参加に対してIOCも協力を約束した今、北韓の積極的な対応を期待します」と呼びかけた。
これに今年一月、金正恩委員長が「新年は、わが人民が共和国創建七〇周年を大慶事とて記念することになり、南朝鮮では冬季五輪競技大会が開かれ、北と南の双方にとって意義のある年です。われわれは民族的大事を盛大に執り行い、民族の尊厳と気概を内外に轟かせるためにも、凍結状態にある北南関係を改善し、意義深い今年を民族史に特記すべき画期的な年として輝かせなければなりません」と応え、二月の平昌五輪は朝鮮半島の和解の新たな歴史の序章となった。
三月初めには、文在寅大統領の特使たちがピョンヤンで金正恩委員長と、ワシントンでトランプ大統領と会談し、南北首脳会談と朝米首脳会談の開催が決まった。冷戦終結の第一章が始まった。
四月二七日、まず板門店で南北首脳会談が行われた。軍事境界線を徒歩で超えた金正恩委員長。「金委員長は南に来たけれど、私はいつ(境界線を)超えられるのでしょう」という文在寅大統領の言葉に「ならば今超えてみましょうか」と金委員長。両首脳が手をつないで境界線を越える姿が、第一章の一ページ目を飾った。そして前途を照らす「板門店宣言」が発表された。
同日の晩さん会では「こうして同じ場所に座るまで皆よく耐えました。互いに拳を挙げたこともありました。別れた家族に会えない悲しい歳月もありました。けれど今日私たちは全世界が見守る中で歴史的な話し合いをして貴重な合意をしました。韓半島と全世界の平和のための新たなスタートが切られました」という六十代の文大統領の温かい言葉に胸を熱くし、「今日の出会いと成果は始まりに過ぎません。これから私たちがやるべきことに比べれば氷山の一角です。私たちの前途は決して平たんではありません。私たちの前には全く新しい挑戦や障害物が待っているはずです。しかし少しでも恐れたり、大変だからと顔を背けて避けたりする権利は私たちにはありません。(私たちは)代わりのいない歴史の主人公です。私たちがやらなければ、誰もできない仕事を担っているのです」という三十代の金委員長の血気みなぎる言葉に力を得た。冷戦終結に向けた第一歩が踏み出された。
五月に入り、朝米首脳会談の日程が発表された。六月一二日、シンガポール。この会談を前に明日二二日、文在寅大統領がワシントンを訪問し、韓米首脳会談が開催される。板門店での会談で両首脳は「スピードが大切」と強調した。冷静にスピーディーに軽やかに、障害物の間を飛び越えていってほしい。
◇ ◇
南北首脳会談が行われた四月二七日、私は名古屋地裁前で「無償化」裁判の判決を待っていた。裁判所から出てきた弁護士の二人が「不当判決」「差別行政を追認」という紙を開いた瞬間、それまでざわざわしていた周りが沈黙に包まれた。判決に期待していたわけではなかった。ただ朝鮮半島の冷戦終結の幕開けと、朝鮮学校を排除することは合法だとする判決のギャップを目の前に、唖然としていたのだ。
判決文は、民族の歴史や文化、言葉を学んでアイデンティティを確立する権利は「憲法の趣旨において十分に尊重されるべき」だが、「不当な支配」の下で行われる朝鮮学校の民族教育を、公費で支援しないことは合法だと述べた。私たちの何が「不当」で、日本の何が「正当」なのだろうか?その判断基準は何で、日本の文科省はそれを判断できる絶対的な「正」だとでもいうのだろうか。ふと昨年千葉市が、美術展に展示された神奈川朝鮮高級学校・美術部生徒の「慰安婦」をテーマにした絵が、韓日合意に反するという理由などで、美術展への支援を打ち切ったことが思い出された。
南北朝鮮の和解が進み、朝米会談の準備が進む一方で日本は、広い公海上で朝鮮籍の船ととなり合って「不法な積み替え」をしていないかと外国籍の船まで取り締まって「北朝鮮への制裁」の徹底に励んでいる。その執念には、朝鮮への憎悪さえ感じる。冷戦で凍てついていた朝鮮半島にようやく訪れた春は、これまで氷の下に隠れて深く広く根をはっていた彼らのどす黒い差別意識を浮き彫りにしたようだ。
東アジアでの冷戦が終わりを告げようとする今、改めて清算されるべきは、私たち朝鮮人の歴史を捻じ曲げ、文化や言葉を奪い、尊厳を踏みにじって来た日本の朝鮮への植民地統治の歴史であり、その後の七十年余りの在日朝鮮人への弾圧の歴史だ。これこそは差別を生み、ながきに及んで助長させてきた根源である。これらの歴史を清算して、日本の「不当」性をしっかりと歴史に刻まない限り、外交や日本社会に吹く風の流れ次第で、私たちの孫やその子どもたちに再び今のような人権蹂躙が繰り返されないとも限らない。(編集部・金淑子)49
スポンサードリンク